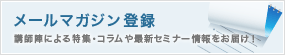- 「人材開発ソリューションのエム・アイ・アソシエイツ株式会社」ホーム
- 経営・人事コラム
- 【コラム】「ジャイロ経営」の薦め (10)
第10回 先達の理論に学ぶ
(2):J.C.アベグレン
1967年夏の「日本の経営」との出会い:
私の「日本の経営」というテーマとの最初の関りは、1967年夏の故J.C.アベグレン氏との東京での出会いでした。
上智大学の4年生だった私と、同級生の日野博之氏(元国際通貨基金ディレクター、現在は東京、米国ワシントンをベースに経済コンサルタントとして活躍)、加藤春一氏(元東京エグゼクティブ・サーチ㈱社長)の3人は、故R.J.R.バロン神父・教授からアベグレン氏を紹介されました。溜池のオフィスを訪れたところ、当時ボストンコンサルティンググループ(BCG)の日本法人の設立準備中で多忙を極めていていたアベグレン氏は、我々とのアポイントメントを忘れていて、結局その日は会えませんでした。このことを教授に報告したところ、「たとえ学生でも約束は約束、抗議するのが当然」ということになり、抗議の結果、当時の学生にとっては夢のような存在の、溜池のアメリカ大使館前にある「ざくろ」の昼食に招待されることになりました。多少大げさな表現をすると、これが最初のグローバルなビジネスの体験だったような気がします。
その昼食がきっかけとなり、その夏、私はアベグレン氏の個人的なアシスタントとして、設立準備中のBCGの前身であるアダムス社で、アルバイトをすることになりました。偶然にも今でいうインターンシップの機会に恵まれたわけですが、卒業後の進路を決めかね、とりあえずアメリカかオーストラリアの大学院への留学の為の奨学金を探していた私にとって、正に人生の岐路となる決定的な出会いとなったのです。
1958年版「日本の経営」(The Japanese Factory):
アベグレン氏は、1958年、MITプレス出版の「The Japanese Factory」(当時の日本語版は占部都美監訳「日本の経営」ダイヤモンド社、2004年に山岡洋一訳の<新訳版>が日本経済社から刊行)の著者であり、日本人論が盛んに議論され始めていた当時、いわゆる「アベグレン旋風」を起こした人として、既に大変に有名になっていたのです。「日本的経営」のテーマでは古典となったこの本は、80年代に盛んに日本企業あるいは「日本株式会社」の強さの源泉としてもてはやされ、三種の神器といわれた「終身雇用」・「年功序列」・「企業内組合」を日本的経営の特長であるとし、日本経済あるいは日本企業の成長・発展の原動力として積極的に位置付け、評価していたのです。
「和魂洋才」と「戦略的考察」:
確か「日本市場への戦略的考察」というテーマのアベグレン氏による小冊子において、「日本では社会と共同体の構造が欧米のものとは違っているので、日本の企業と経済組織も欧米のものと違っていなければ成功しない」といった主旨の戦略的提案を書かれていたことが記憶にあります。「日本の経済力は国内外で開発された技術に基づいているが、その技術を活用できるのは、それを使う企業の組織がきわめて日本的だからである。社会制度が違えば、技術を活用するために必要な経営制度も違うはずだ。」といった内容だったと思います。それを読んだ時、ふとバロン教授のゼミの教室で討議した「和魂洋才」という言葉を連想したことと、「戦略的考察」という聞きなれない言葉が強く印象に残ったことを覚えています。この二つの言葉はその後、私のキャリアの中で大変に重要な意味を持つことになりました。
「会社社会主義」と人生観・ライフスタイル:
日本精工㈱(NSK)のニューヨーク駐在員の時にエネルギー危機が起こり、その最中に、ニューヨークのジャパン・ソサエティー主催のセミナーで、アベグレン氏に偶然再会しました。当然の事ながら、ウォール街のアナリストを中心とした米国実業界のセミナー参加者は、「エネルギー危機の影響で二桁のコストプッシュインフレーションに悩んでいる日本企業・経済の将来」については否定的でした。しかし、アベグレン氏は大方の期待を裏切り、「日本経済は必ずこの危機を克服する」と断言したのです。この時、壇上の氏から突然意見を求められ、私の率直な感想として、「日本企業は、ごく日本的な企業の論理で危機を乗り切ってゆく」といったような内容の回答をしたのを覚えています。しかし、当時の私にとっての関心は、むしろ「その日本的な企業の論理が自分自身の人生観・ライフスタイルと合致したものかどうか」という点にあり、その後この疑問は、より大きなものとなって行きました。統制のとれた、一種の「会社社会主義」下の日本企業と日本経済は、世界の予想と期待をはるかに越えて、アベグレン氏の予測したように見事に危機を脱しました。その後「日本株式会社」と呼ばれるようになったこのシステムは、飛躍的な成長と発展を遂げることになったのです。又、この時の経験がきっかけとなって生み出された多くの省エネ技術は、現在の地球環境問題への比較優位を持つ日本の技術として、世界的な評価を得るに至りました。
2004年版「新・日本の経営」:
本書の冒頭で氏は、戦後わずか60年という短期間に、日本を世界でも類を見ないほど豊かで社会が健全な経済大国にした真の原動力は民間企業であり、その成功を支えた概念、すなわち「欧米の技術革新の成果を導入し、それを完全に日本的価値観による組織で活用する賢明で独自な方法」こそ「日本的経営」だとしています。そして、その「日本独自の方法の開発は、社員の採用、研修、報酬や、労働組合との労使関係、さらには政府、金融機関、株主との関係にも及んだ。それらは全て人間に関わる部分であり、日本企業は、企業を構成する人間が経営システムの中心に位置している会社という共同体であると」して、変革ではなく継続性が主題であるとし、「終身雇用は終わった」という当時の内外の論調に反論しているのです。
終身の関係(lifetime commitment):
アベグレン氏は、1958年の「日本の経営」で日本企業の雇用慣行を分析し、「終身の関係
(lifetime commitment)」と名付けました。「社会組織としての会社が構成員に対する義務あるいは約束」することを、占部都美訳の初版以来、一般的に「終身雇用制(lifetime
employment)」と呼ばれる様になったものと区別しています。 更に、客観的事実として、近年平均勤続年数は長期化し、会社は社員に対する約束を守り続づけているとしているのです。
しかしながら、一般的な世界の論調は、日本的経営はあくまで特殊で例外的なものであり、その雇用制度と経営方法が英米型に近づいてゆく形で解消されてゆくはずとの前提に基づくものが多いのも事実です。特に格付け会社のムーディ?ズ・インベスターズ・サービスが、終身雇用制が日本の大企業の競争力を低下させ、信用力をも低下させるとし、トヨタ自動車の格付けを引き下げたことはその典型です。
氏が主張しているように、確かにムーディーズの決定が昨今評判の悪いアメリカ的ドグマによってなされている感は否めませんでした。多くの経営的指標において世界最強の自動車メーカーであるトヨタの強さの所以が、絞り込まれた世界的規模の経営戦略と優秀な従業員の会社方針・ブランド価値へのコミットメント・忠誠心にあることは間違いのない議論です。ここでの問題は、それが「終身雇用制」によってのみによって達成されたかどうかという点にあるわけです。
先の章でもお話ししたように、この問題を解く鍵は、「ジャイロ経営」がテーマとしている「コミットメント」という言葉の意味にあると私は考えるのです。ですから「戦略的経営」や「成果主義」も、この様なコミットメントが確保されている企業においては上手く機能するのです。
「年功序列」・「企業内組合」における変化:
いわゆる「三種の神器」の第二の柱である「年功序列」による昇給と昇進に関しては、本著では「どのような社会においても昇進と昇給にあたっては年功を考慮するし、日本の企業においても完全な年功序列がとられてきたわけではない」とした上で、現在では多くの企業が年功主義を中心に成果主義を一部取り入れており、トヨタや日立、松下電器、キャノンの年齢給廃止の例からも見られるように、この制度が急速に消えようとしていることを指摘しています。
第三の柱である「企業内組合」制度に関しては、共同体としての日本企業において、全員が共通の利益のために協力する仕組みである点は、50年後の現在でも本質的には変化してはいないと分析しています。しかしながら、現在の労働組合はいまや20パーセントを下回る組織率で、その役割は低下し、賃上げは過去の闘争によって、労働条件の改善は法改正によってほぼ達成され、賃金よりも雇用確保を重視して、労使の対決を避けており、成長部門としてのサービス産業の拡大と労働力の平均年齢の上昇や、専門技術保持者の派遣社員としての雇用といった構造的な環境の変化もこの傾向を助長しているとしています。
変化に適応してゆく日本的経営:
本書では具体例として、トヨタ、キャノンがこの日本的経営、特に「終身雇用」を最大限に活用して成功を収めている事実が、失敗した米国のボーイングの例との対比で説明されているのは興味深いことです。経済状況の変化を理由にレイオフと解雇を大規模な雇用調整の主な手段にする英米企業に対し、日本企業は残業の削減、従業員の配置転換、採用の絞り込み、関連会社への正社員や臨時社員の出向・転籍など、需要の変化の影響を和らげる社内の仕組みを使っています。
これらの勝ち組の日本企業の成功は、いわゆる「失われた10年」の間に、必要な事業の再調整と再設計を断行し、過去の長く続いた高成長下で多くの企業が安易な多角化という戦略的失敗に陥った中で、「ひとつの事業に絞込み、その事業で支配的の地位を獲得した後にはじめて次の事業に進出し、その事業で支配的な地位を獲得する」というGEのジャック・ウェルチ的な「絞り込みの戦略」を実践した結果であるとしているのです。
又、この再設計や再構築の過程においても、例えば報酬の成果主義や企業統治といった分野で、「変革」と称して米国流を猿真似した安易な変更にを行って、「日本的経営」特に「終身的関係」に基づく経営システム基盤から離れる動きをとることによるリスクが、極めて高いとしています。
1970年代のNSKの国際化戦略:
当時日本企業は、米国企業に比べ、より長期的な視野に立って事業展開をおこなうと一般的にいわれていました。
第二次世界大戦の戦災を比較的少ない被害で切り抜けた日本精工(NSK)は、戦後旧安田財閥、芙蓉グループの「転がり軸受(ベアリング)」メーカーとして、財界四天王の一人としても著名だった今里広記社長の強い指導力、特に労働争議対策や財界との太いパイプに基づく諸施策によって、国内軸受業界でナンバー・ワンの地位を築き、めざましい発展をとげることになりました。
私の入社した1970年のNSKでは、競合の光洋精工やNTN東洋ベアリングに比べて弱いと考えられていた、「事業の国際化」が最大のテーマでした。主に、製品の海外における現地販売子会社を通して輸出販売を担当する貿易部と、海外への軸受け製造設備のプラント輸出および海外軸受け製造拠点への直接投資を担当する海外事業室の2部門が、小島慶三専務の「国際化ビジョン」の下に積極策を展開中で、私は後者に配属されることになりました。
私が配属された当時の海外事業室は、チェコスロバキア・ブルガリアへの軸受け製造の為のプラント輸出が成功に終わり、次の重要プロジェクトとして、オ?ストラリア・ブラジルでの軸受製造工場の直接投資による建設が進行中という状況にありました。新入社員の私の最初の職場は、留学経験を活用出来るということもあり、当時多摩川工場にあったオーストラリア工場の建設チームでした。
オーストラリアへの海外直接投資と戦略構想:
このプロジェクトは、NSKにとって初めての海外工場であり、国内産業の保護色の強いオーストラリアへの進出ということで、現地メーカー(英国の RHP社の直接投資による子会社)が生産していた主要型番以外の型番の小径軸受の製造工場としての進出という形態をとりました。オーストラリア政府はもとより進出先のビクトリア州ジーロン市では予想以上に歓迎されましたが、英国的労働組合の強い影響と、白豪主義といった独特の歴史的背景を持つ産業別・職種別労働組合との関係は大きなリスクと考えられていました。
結果的には、当初心配された、30数人の小さな工場に3から4の異なった組合に属する組合員が働くという労使関係の困難さよりも、むしろ客先メーカーのほとんどがオーストラリアから撤退するという市場の変化の中で、他社の非生産型番の小型軸受の製造という事業自体が、その規模の経済を失ったことが原因となり、オーストラリア工場は1979年に閉鎖されることになりました。しかし、この時の海外直接投資及び製造活動に関わる様々な経験は、その後ブラジル、米国、英国への工場進出を成功させる上での貴重な経験となったのです。
日本国内の競合他社がコスト削減の為に工場の操業度維持を目指した結果、過剰生産分の低価格輸出を強いられていた状況と比較して、当時のNSKが採った積極的な海外に於ける現地生産という海外事業展開の方向性は、圧倒的に優位な国内市場における占有率もあって、比較優位性(Comparative advantage)を持つものでした。一方この低価格輸出の問題は、1970年代には「ダンピング問題」として米国のみならずカナダ、オーストラリア等で提訴され、紛糾することとなりました。
その頃、アベグレン氏率いる日本BCGから、「日本経営の探求」と、エクスペリアンス・カーブ(Experience curve)が紹介された「企業成長の論理」、そしてプロダクト・ポートフォリオ・マネージメント(Product Portfolio Management)が展開された「企業戦略の構図」の三部作からなる「企業戦略の展望」シリーズが発刊され、その動態的企業分析と戦略的提案に触れた私は大きな影響を受けました。
オーストラリアのプロジェクトが軌道にのり、本社に戻った私は、「NSKインターナル戦略構想」という表題の小論文で、この事業の国際化に関連した様々な将来的課題を検証し、経営戦略論でいうところの、いわゆる「組織能力」(Organizational capabilities)の改善提案を行いました。この提案は、経営陣や企画・営業部門の一部では予想を越えて話題にはなったようですが、会社における基本的な評価としては、「新入社員の変わった提案」の域を出なかったのです。
市場占有率(Market Share)か、投資回収率(Return on Investment)か:
1972年からの勤務先となった米国市場は、1970年代のNSKにとって大きな問題でした。この頃になり玉軸受をアメリカ市場において"Hoover" ブランドで販売する、OEM契約の相手先であるHoover社の米国市場における基本的販売力が疑いを持たれるようになり、NSKはHoover社に対し、「日本の競合他社の米国市場における実績との比較においても、市場占有率とその改善努力が不充分だ」と主張し始めていました。一方、戦後の日米関係をそのまま写した様なHoover社の長年の厳しい品質要求の結果、Hooverブランドの玉軸受は米国市場では最高の品質の評価を受けるまでになっていて、特にその低音響性能は業界一とされていたのです。
Hoover社の経営陣にとっては、日本側のいう市場占有率を獲得する為に採られるべき諸施策は、キャシュフロー的観点、つまり投資回収率(ROI)からみて株主を説得出来るレベルでは無いとし、両者の交渉は平行線をたどったのです。後に両社は50%/50%の合弁の米国法人を設立する事になりましたが、1975年合弁会社は解消され、NSK100%の子会社となったのです。NSKは、その後さらにアイオワ州クラリンダに最新鋭設備の製造工場を建設し、米国市場において念願の"NSK"ブランドによる玉軸受の製造販売が実現したのです。
NSKと米国市場のパートナーであるHoover社との間で行われた「市場占有率(Market
Share)と投資回収率(ROI)を巡る論議は、同時期にBCGによって提唱されたポートフォリオマネージメントの経営戦略論や、その後世界市場を目指した多くの日本企業の勝因とされる「絞り込みの戦略」を彷彿とさせるものでした。いずれにしてもNSKはHoover社の軸受部門を買収する形で「NSK ブランドによるアメリカ市場における製造販売体制の確保」という中長期的な目標を達成したのです。
「終身的関係」からの新たな出発:
1979年、私は入社以来、ニューヨーク、トロントの駐在経験を含め、約10年間在籍した日本精工㈱を辞めました。直接の理由は、会社の先輩のはじめたベンチャービジネスに参加する為でしたが、「終身的関係」からの脱出が本当の理由であったという個人的な経験の話は、前の章で述べたとおりです。
さきに述べた理由以外にも、この時期に、敬愛していた今里社長が会長に、小島専務が芙蓉石油開発㈱の社長として転出するという経営首脳陣の交代があり、シュンペーターの定義した、「企業家による経済的諸要素の新結合による革新によって創り出される創造的破壊過程によって、動態的かつ不連続に発展してゆくグローバルな経済社会」での活躍を夢見て、その為の準備をしてきたつもりの私には、会社との隔たりが益々大きくなったように感じられたのです。特に大学に於ける恩師で、NSKの「国際化ビジョン」の提唱者であった、敬愛する小島氏の石油開発部門への転出は私にとって大変に残念なことでした。
先にも述べましたが、E.F.シューマッハ?の「スモールイズビューティフル」の訳者でもあった小島氏は、レスター・ブラウンの「飢餓の世紀」の訳者でもあります。そしてさらに「文明としての農業」・「農に還る時代」・「農業が輝く」の農業三部作や、「文化としてのたんぼ」での新しい切り口による新農業論で知られています。「人間復興の経済学」・「人間復興の時代」でのヒューマノミックスの提唱や、「江戸の産業ルネッサンス」による江戸時代の再評価といったユニークな視点を、多岐な分野にわたって展開され、私もその頃から参加し始めた「小島志塾」における勉強会は、全国的な広がりを見せることになり、各地における塾出身の人々による種々の活動が、今でも多くの人々をひきつけています。
ところで、この小島志塾で学んだシューマッハの理論は、現代社会においては、アダム・スミス以来の経済学が資本主義の基本原則としてきた「規模の経済」が妥当しない状況、つまり「大きいこと」が必ずしも良いことでは無いという「規模の不経済」が、いたるところに存在するというものでした。
この頃、NSKのOBから自然甘味料ステビアの精製技術によるベンチャーへの参加に誘われ、参画を決めました。それはいわば、大企業においてある種の「規模の不経済」を体感した私が、「明快なビジョン、平坦で参画的な組織、リーダーシップ的経営、戦略的な経営プロセス、明確な職務・業務責任の分担、正当な評価に基づく昇給・昇格、迅速かつ柔軟で選択肢をもった行動的意思決定」等の要素を備えた、自らの理想とする経営を実践するという夢を、小さいその新組織で実現するための出発だったのです。